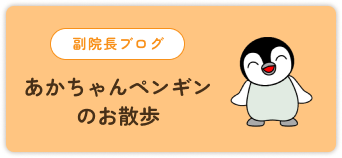赤ちゃん相談について
体重増加、哺乳状態、離乳食、便秘、夜泣き、生活リズム、湿疹、アレルギーなど、赤ちゃんや子育てに関することであれば何でもお気軽に相談してください。

- 早産児、低出生体重児で生まれたから色々心配
- おっぱいは足りているかな?飲ませすぎかな?
- 体重はちゃんと増えてる?増えすぎ?
- うんちが心配(でない・ゆるい・色がおかしい・血が混じっている・・・など)
- 吐くことが心配(飲むたびに吐く、勢いよく吐く、吐いたものに血が混じっている・・・など)
- 頭がゆがんでいる
- おへそが出ている、じゅくじゅくしている
- 肌ががさがさ荒れている
- スキンケアについて聞きたい
- よくわからないけど、これって普通なの?大丈夫かな?
お母さま・ご家族に寄り添って子育てのサポートをいたします。
当院のブログ“あかちゃんペンギンのお散歩”もぜひご覧ください。